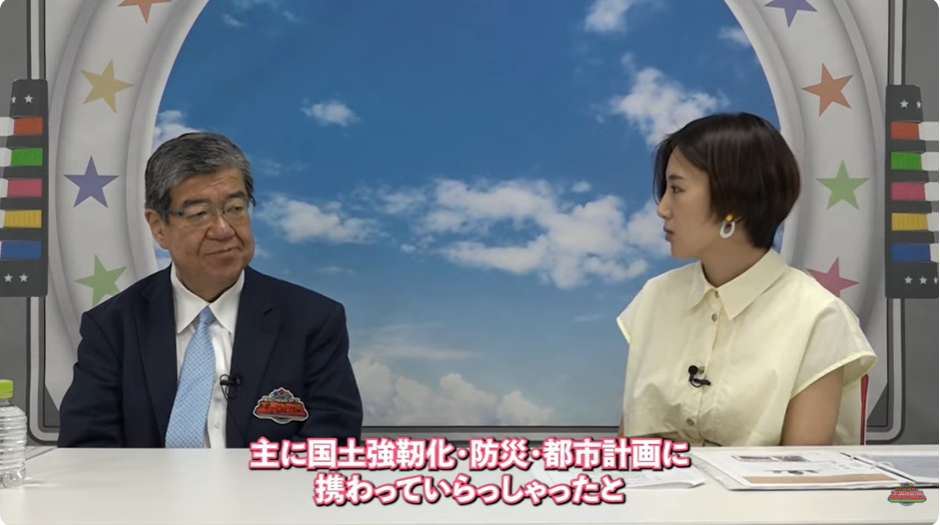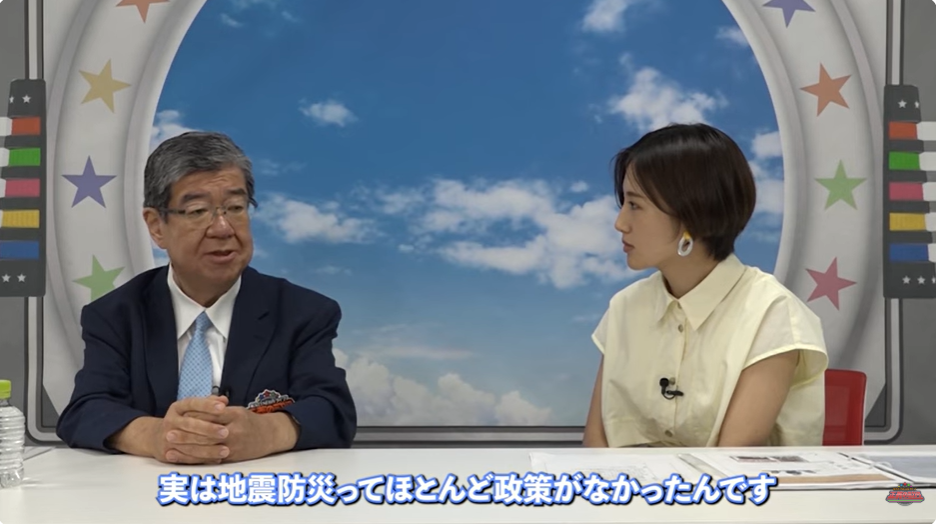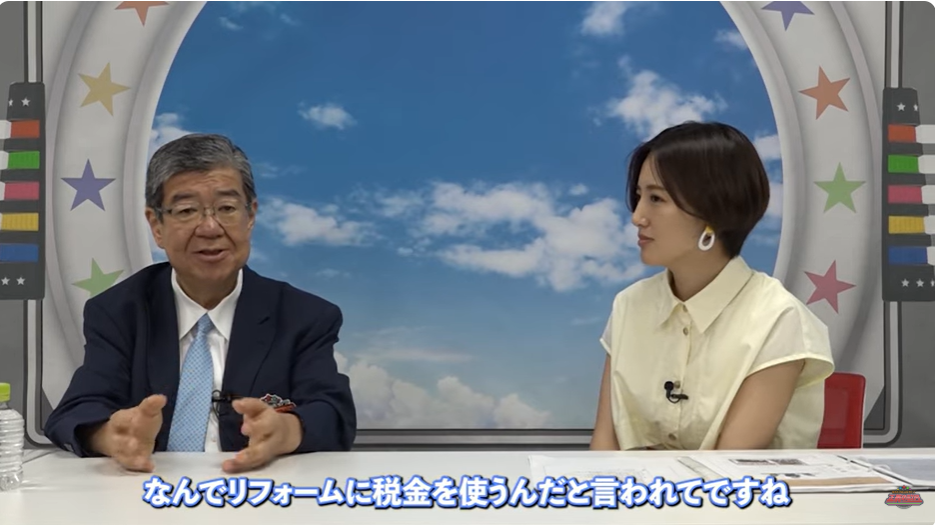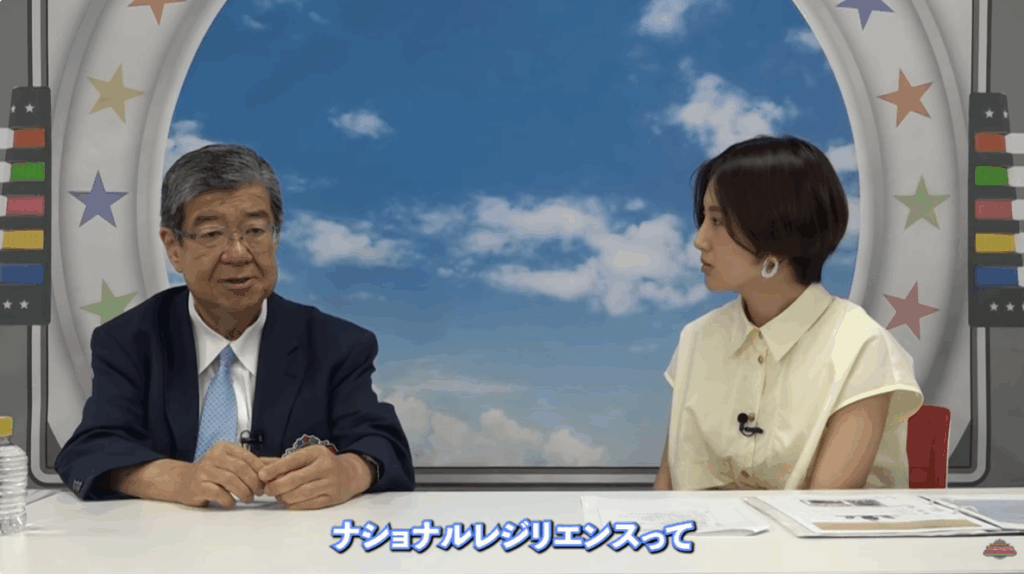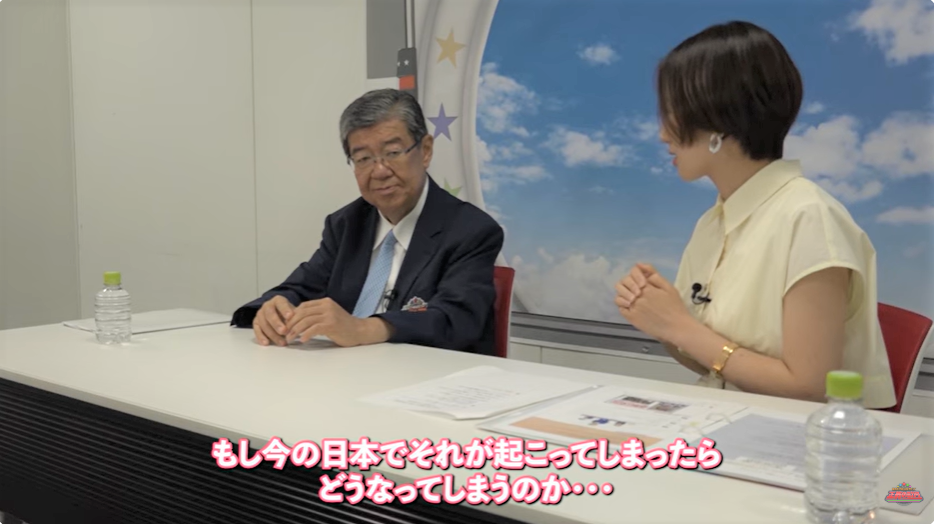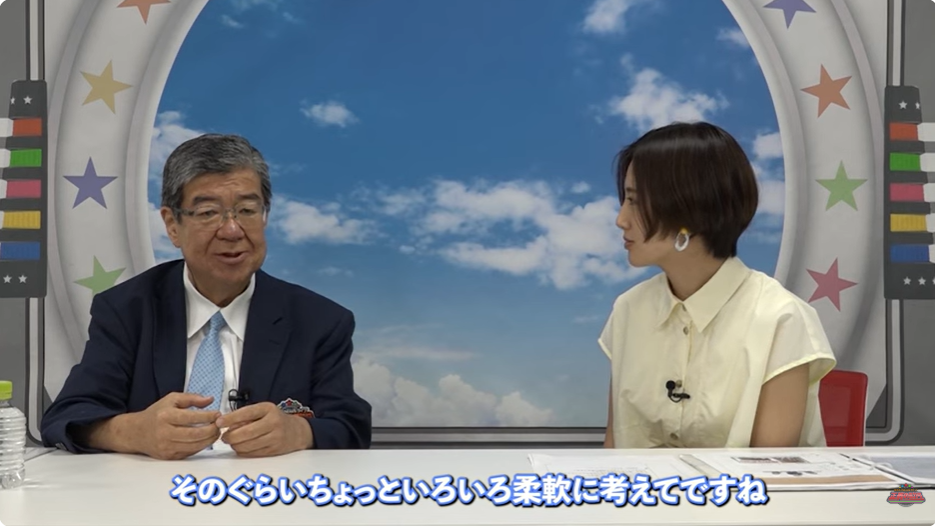もう“あの言葉”を使うのはやめよう。発想を変えて進んできた、日本の防災政策って?『正義のミカタ』YouTube
ニュースの正しいミカタを解説する情報バラエティ番組『教えて!ニュースライブ 正義のミカタ』(ABCテレビ)は、東留伽アナウンサーのMCで番組公式YouTubeチャンネル『正義のミカタチャンネル』でも情報を発信中! 防災・都市計画専門家の渋谷和久氏をゲストに迎えた回では、日本の防災政策の現在地を解説!
番組には外交の解説者として出演する機会の多い渋谷氏だが、実は外交に携わったのは長いキャリアの最後の10年。その前の30年間は、国交省で主に国土強靭化・防災・都市計画に携わっていた。本人いわく「国土交通行政ほぼ全て担当した」なかで、防災の仕事にも長く就いていたという。2011年に東日本大震災が発生した際は、国土交通省の政策課長をしていたそうで、復興政策の取りまとめを任され「かなり大変でした」と語る。
最近ではトカラ列島で群発地震が繰り返されたりと、日本各地で地震が頻発するなか、気になるのは遠からず確実に起きるだろうといわれている大震災への備え。「日本の防災政策って、本当に間に合っているものなんですか?」と質問する東アナに、渋谷氏は日本の防災政策の変化について話し始めた。
実は、1995年の阪神淡路大震災が起きる前、水害については事前対策を行っていたものの、地震については「いつどこで起きるか分からないから事前対策をしてもしょうがない」と考えていた日本政府。そのため、何も事前防災の施策を行っていなかったのだという。
ところが、阪神淡路大震災で多くの方が命を落とし、その大半は家が潰れて亡くなったことから、住宅の耐震化を進めれば命は助かる、これこそ事前防災じゃないかと言われるように。 しかしその当時、内閣府の防災担当をしていた渋谷氏が、財務省に住宅の耐震化の予算要求を行ったところ「住宅は個人の財産だから」「リフォームと一緒じゃないか、なんでリフォームに税金を使うんだ」と言われ、説得には大変な苦労をしたという。
まずは、道路に面している住宅が倒れると避難に支障をきたすという理由で、そうした立地の住宅には国費を入れてもいいじゃないかと説得を開始。そこから範囲を広げ、今はほとんどすべての自治体が住宅の耐震化を補助するようになっている。
その後、東海地震や南海トラフ地震、首都直下地震など歴史的に確実に起こることが分かっている地震については「ちゃんと被害想定を出して国民に明らかにするべきだ」と働きかけたという。それに対しても「国民が怯えるだけだ」と反対の声があったそうだが、粘り強く交渉して公表に踏み切り、事前防災をすることで被害は減らせるんだということを政策として打ち立てようと努めた、と渋谷氏。それから20数年を経て、地震防災については「だいぶ事前防災というものの政策ができてきた」と話す。
その仕上げにあったのが「国土強靭化」という考え方だ。英語ではナショナルレジリエンスといい、世界中で取り組まれている。たとえば道路は単なるインフラではなく、そういったものを整備することが事前防災に役立つ。そうした考え方をすべての政策に広めようということで、2013年に内閣官房に「国土強靭化推進室」が誕生。その初代担当には渋谷氏が就いたという。現在では政策も充実してきて、予算も増えているため「あの時の取り組みは無駄じゃなかったなと思います」と渋谷氏は振り返る。
7月に放送された「正義のミカタ」では、京都大学名誉教授で地震専門家である鎌田浩毅氏が科学的な考慮をもとに「2035年の前後5年にほぼ確実に南海トラフが来る」と発言。その地震の規模は東日本大震災の10倍以上になるだろうと話し、東アナは「もし今の日本でそれが起こってしまったらどうなってしまうのか…怖いんですよね」と不安を打ち明ける。
2024年に南海トラフの臨時情報が初めて出たことで、一部混乱した向きもあるものの、それによって国民の皆さんの意識も少し変わってきたと渋谷氏。「リスクについて正しく伝えて、どうしたらいいかを国民の皆さんと一緒に考えるということがすごく大事じゃないかなと思います」とコメント。
さらに、渋谷氏は東日本大震災の教訓として「もう○○○って言葉を使うのはやめよう」とも語る。東日本大震災の直後にもメディアでよく耳にした、その言葉とは?
配信の終盤には、防衛費を含め「ちょっといろいろ柔軟に考えて」、日本の国土を守るために必要な予算を手当てしようと訴える渋谷氏。お米の高騰が社会問題になっているが、実は米農家を維持することも“国土強靭化”を進める上で見逃せないという。渋谷氏が指摘する、米づくりの重要な役割とは?
番組公式YouTube『正義のミカタチャンネル』は、東留伽アナのMCで、地上波には入りきらなかったトピックも深掘り解説中!