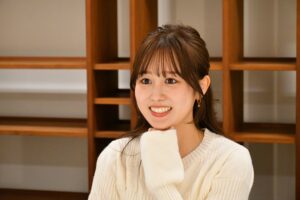もともと旧石器時代にアレを運んでいた道!?日本最古の国道「竹内街道」 聖徳太子ゆかりの名寺&レトロ喫茶でアナウンサー2人がまったり
ABCテレビの柴田博アナウンサーと中村想人アナウンサーが、古くから街と街をつないできた「街道」を歩きながら深い歴史や人の営みに触れ、街の魅力を再発見する「柴田・中村の街道しゃべ歩き」。今回は「竹内街道」の第3章をお届けします。
竹内街道は、大阪・堺市と奈良・葛城市を結ぶ約26km。613年、推古天皇が大阪から当時の都・飛鳥を結ぶ道として整備した日本最古の国道です。前回までに堺市から松原市までの約8kmを歩いてきた2人。今回からは松原市を抜け、羽曳野市へとつながるおよそ9kmの道のりを進みます。
まもなく見つけた石碑のそばにある説明板によれば、ここには1万年以上前の旧石器時代から人が暮らしていたとのこと。竹内街道が整備されるおよそ1400年前よりずっとずっと昔から、ここには人が集まる“何か”があったよう。それは一体何なのか? 新たな謎に2人は興味津々です。
松原市を抜けて羽曳野市に入り、しばらく歩くと、市の創生を願って建てられたという高灯籠が。その横にある石碑には、竹内街道に関する解説が刻まれていて、“旧石器時代には石器の材料であるサヌカイトを運ぶ道”との一文に、先ほどの謎の答えを見いだした柴田アナは「これだ!」と大興奮です。
つまり、竹内街道は何もないところに突然開通したわけではなく、もともとあった「石を運ぶ道」をいかした道だったのです。旧石器時代と街道の深い関わりを知った2人は、この後、石碑に書かれていた聖徳太子ゆかりの寺「野中寺」へ。
1400年ほど前、聖徳太子と蘇我馬子が建立したと伝えられる「野中寺」。その歴史を教えてもらおうと2人が電話をかけたのは、「街道しゃべ歩き」ではすっかりおなじみ、大阪の歴史にくわしい作家で古地図コレクターの本渡章先生です。
先生によれば、創建当時の「野中寺」は現在の倍ほど広く、塔や金堂の並ぶ配置が奈良の法隆寺によく似た荘厳なお寺だったとのこと。後に合戦などによって焼失した塔や金堂の跡が今も境内に残っています。
そして、「野中寺」と書いて「やちゅうじ」と読む寺の名前は、このあたりの地名が「野中(のなか)」だったことに由来するそう。「のなか」をわざわざ「やちゅう」とした理由は明らかではありませんが、「“のなかのおてら”より“やちゅうじ”の方が立派な感じしません?(笑)」と本渡先生。単純に「かっこいい」からそう読ませたのでは?と大胆に推理します。
「お寺の名前って、かっこいいとかで決まるもんなんですか?」と疑問を呈する中村アナですが、先生はニッコリ笑って「そういうもんです」と。そんなユルい結論に大笑いしながらも「先生が言うから間違いない!」とちゃっかり乗っかる柴田アナから、「上の人が言ったらそうなる!」、「それが世の常!」と力説されて納得せざるをえず…。
【動画】羽曳野市に入ると、“国道”とは思えないほど細い道が出現。道を間違えそうになるハプニングをきっかけに、柴田アナが「深そうで浅〜い」人生哲学を語る!?
さて、歩き始めておよそ3時間。お腹も空いてきた2人は、街道のすぐそばにあるレトロな喫茶店で一旦、休憩です。創業はおよそ45年前と、地元の人に長年愛される老舗で、中村アナは親子丼、柴田アナはカレーをガッツリいただいた2人。お腹も満たされたところで、お店の人がオススメする公園に行ってみることに。
訪れたのは、店をでてすぐの場所にある「峰塚公園」。園内には世界文化遺産に登録されている「百舌鳥・古市古墳群」を構成する古墳のひとつがあり、こちらになんと登ることができるんです。
小高い丘のようになっている古墳をのぼると、緑豊かな景色が一望! 遠くに見えるのは二上山で、山を越えた先に目的地がありますが…。ここまで10mほどをのぼるだけでも息が上がっていた柴田アナに山越えはできるのか?「大丈夫ですか?」と不安そうな中村アナ。「エイエイオー!」と気合いは十分の柴田アナとともにしゃべ歩きはまだまだ続きます!
「柴田・中村の街道しゃべ歩き」は、10月2日(木)放送の『newsおかえり』(ABCテレビ 毎週月曜〜金曜午後3:40〜)で紹介しました。